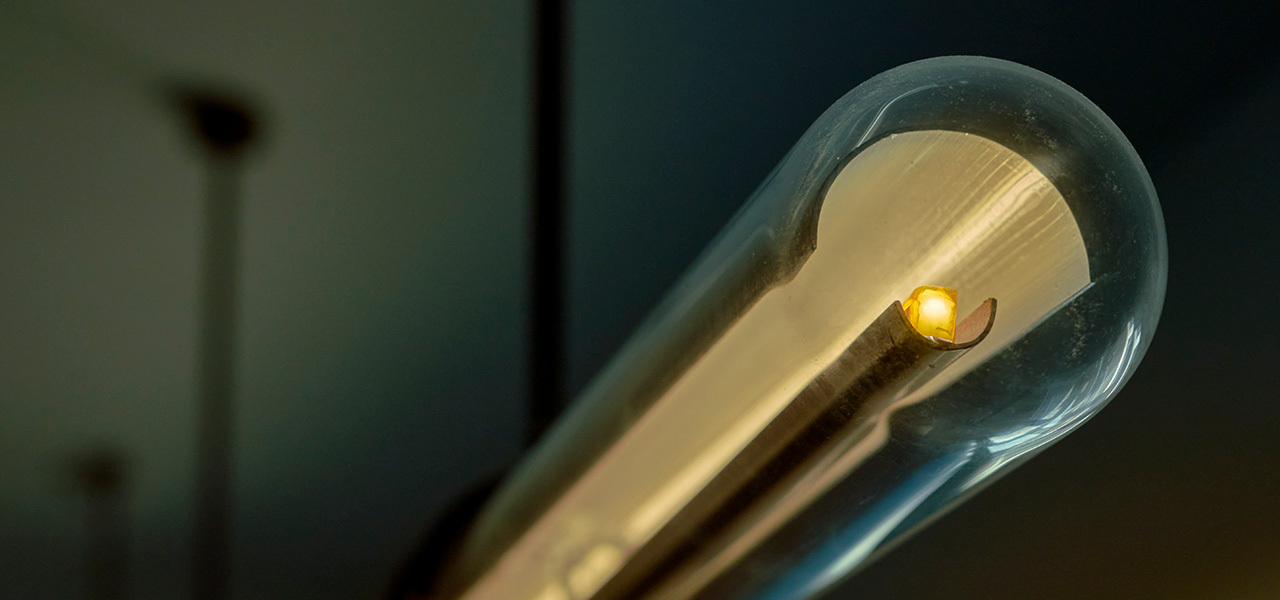
ものづくりへの灯火
── 変化しながら思いを繋ぐ
2025.4.25
デザインと技術で、ユーザーにハピネスを届けてきたフェンリル。創業から20年を迎えようとする中で、自社開発事業と共同開発事業への思いや姿勢は変わらない。
そうした中でも新たな挑戦を続けており、2022年4月には新部門のND部を設立。NDとは「New Design, Development, Discovery」の略称で、フェンリルの共同開発事業を特徴付ける「新領域を作る」という意味が込められている。
ND部設立の核となったのは、共同開発事業の黎明期から現在まで、PMとして第一線で活躍してきた河岸。これまでのキャリアやND部設立の経緯などを通して、チーム力を高めるための取り組み、クライアントとの関係構築、クライアントとユーザーの期待を超えるものづくりへの考え方と姿勢に触れる。

好奇心をエネルギーに
IT業界への興味はいつ頃からあったのでしょうか?
大学生当時、ちょうどインターネットが普及し始めていた頃で、ただ便利なツールというより、その仕組みに可能性と面白さを感じていました。特にホームページの表層を作るところに興味があったので、独学でデザインを勉強してページを作ったりしていたんです。
元々は文系の学部だったんですけど、デザインへの興味を仕事にしたくて、大学卒業後はウェブデザイナーとしてキャリアをスタートしました。
最初はデザインに興味を持っていたんですね
そうですね、ですが、実際にデザインの仕事をしてみて自分にはデザインセンスがないなと気付きました。何かしらの目的や意図があってデザインをするのは好きでしたが、自信のあるデザインができても他のデザイナーのデザインが優れていることや、上司からの指摘を納得できないなど、デザイナーとしての感覚や審美眼が弱いと思ったんです。
デザイナーとしてのキャリアに悩んでいたときに、プログラミングに触れる機会があって。使用する言語を正しく入力すれば、想定通りの動作をするプログラミングの世界が性に合っていると思い、同じ会社でウェブエンジニアにキャリアチェンジしました。
エンジニア職へのキャリアチェンジ、どのように技術を身に付けたのでしょうか
開発に関する本やオープンソースはあったので、そこから独学で色々と勉強しました。それに加えて、仕事を通して実践的な知識と経験を積み重ねていったという感じです。
デザインを勉強しているときもそうでしたが、勉強がつらいと思ったことは一度もなくて。学べば学ぶほど、アウトプットしたときに自分の成長が目に見えたので楽しかったです。自分が書いたプログラムが画面上で動いたときの感動は今でも記憶に残っていて、その瞬間の楽しさや、やりがいみたいなことが、今に生きているのかなと思います。

エンジニアとして積んできた経験について教えていただけますか
2社目はウェブエンジニア、3社目ではPMとしてスキルを磨きました。ただエンジニアとしてキャリアをスタートしたときには、PMを目指そうとは全く考えていなかったんです。クライアントワークでPMのリソースが足りず、たまたま私が担うようになったことをきっかけに、PMを務めるようになりました。
PMを始めた当時は、先輩の一挙手一投足を盗みながら成功と失敗を積み重ねていたことを覚えています。PMのスキルを磨くには座学だけではなく、とにかく色んな経験が大切なので。現在も、学ぶ姿勢を常に意識できているのは、そのときの感覚が染み付いているからだと思います。
新たな環境であるフェンリルに入社して、これまでの経験とギャップを感じた部分はありますか?
Sleipnirを使っていたので、フェンリルのことは元々知っていて面白い会社だなと思っていました。転職を考えた2013年当時、フェンリルの共同開発事業はアプリしかなかったのですが、新たにウェブ開発を担う「共同開発2部」が立ち上がりました。ウェブ開発に携わることに興味があったのと、前職でお世話になった方からの紹介もありフェンリルに入社しました。

これまでの私の経験や感覚では、例えば業務システムの画面デザインはシステムエンジニアがするものでしたが、フェンリルはそうではなかったんです。
フェンリルではそれらをデザイナーが受け持つ体制や文化があり、デザイナーとエンジニアが密接な関係で仕事をしていて、そういう部分にポジティブな驚きがありましたね。
フェンリルで長く活躍している河岸さんの視点で、ならではの文化だと感じることは何かありますか?
入社当時から今も変わりませんが、フェンリルには専門分野に特化した人がたくさんいます。専門性を持った人たちを尊重し、彼ら彼女らが主役というのも面白い文化だなと思います。デザインと技術という手段をあえて突き詰めて、本質を見いだそうというマインドも、面白いし変わらないところです。
ここ数年でいうと、エンジニアが中心となってテックチームが誕生したのも、そうしたマインドが影響しているかと思います。テックチームは「最高のプロダクトやサービスを作ることを目指し、フェンリルのエンジニアリングを推進する」ために組織されたチームです。フェンリルの主要な技術領域ごとに分類されたユニットがあり、そこでエンジニアの個々の能力を向上させる活動をしています。
テックチームのように、専門性を極めるために行動する人や、新たな取り組みを後押しする文化はフェンリルの明確な特徴だと思いますし、フェンリルの好きな部分です。

さらにデザインと技術が融合する場を
ND部の設立の経緯についてお聞きしたいのですが
フェンリルではさまざまなプロジェクトが動いているので、一つのプロジェクトが終わるとチームは解散し、それぞれがまた別のチームにアサインされます。多くのプロジェクトに携わることはメンバーにとって良い経験になりますし、それがまたクライアントへの提案に生かされるのが共同開発の良さでもあります。
ただ、企画からデザイン、そして開発といったフェーズを経てクライアントの理解を深め、知識やスキルを身に付けたことが、関係性も含めていったんクリアされてしまうのはもったいないとも感じていました。

そこで、共同開発で築いた関係性を、より強い結び付きにしたいと考えたんです。プロジェクトごとのチームもあれば、クライアントごとのチームがあってもいいのではないかと。クライアントごとにチームを組織することで、特化した知識やスキルを積み重ねられますし、長くお付き合いを続ける場合は、この体制の方が双方にとってプラスになると考えました。
上層部からも応援いただけたことでスピード感を持って進めることができ、構想から3か月ほど経った2022年4月にND部を設立しました。
現在はデザイナーとエンジニア合わせておよそ35名が所属しています。ND部は、クライアントとより近い距離で長期的にプロジェクトを進めていくので、双方に責任者を立てています。私はフェンリル側の責任者としてやりとりしていて、営業とPM、マネジメントの役割も担っています。
デザイナーとエンジニアが在籍していますが、チームとして力を最大化するために大切なことは何でしょうか
色んな価値観を持ったメンバーが集まった組織でチーム力を高めるためには、相互理解を深めることが重要です。相手の個性や考え方を知り理解することは、お互いの心の距離が縮まり信頼関係を築くための土台になります。その結果、チーム力が強化され、高いパフォーマンスを発揮できるのだと思います。
相互理解を深めるために、具体的にどのような取り組みを?
さまざまありますが、月に一度の部の定例会議で、Good & Newの時間を設けています。毎回ランダムで1チーム5、6名に振り分けて、その月にあった仕事やプライベートでの良いことや悪いことを共有し、仲間の人となりを知れる場です。

また、半期に一度、部署の全員が参加するMeetUpというイベントを実施していて、普段は勤務地が異なるメンバー同士が、オフラインで顔を合わせます。このMeetUpの運営自体も相互理解に生かしたくて、運営メンバーは毎回デザイナーとエンジニアから1名ずつ選んでいます。
デザイナーとエンジニアは視点や考え方が違うので、それぞれが協力して作るものは毎回素晴らしいです。こうしたチームビルディングでの取り組みを通して、業務とは違った仲間の一面を知り、関係性を深めています。
ND部が掲げているミッションや部の存在意義についてお聞きしたいのですが
ND部はユーザーをワクワクさせることを大切にして日々の業務に励んでいます。それが私たちの存在意義にもなると考えています。
ワクワクの内容は二つあって、「シンプルなものでも使い続けたくなるような仕組み」と、「アニメーションやインタラクションのような見た目」を指しています。今はまだ実現できていないことが多いのですが、目標に向かって確実に前進し、ユーザーの期待を超えるものを作るチームや存在になりたいです。
一つの組織、一つのチームで悪戦苦闘しながらも、クライアントと共にものづくりに向き合い続けられる環境があるため、とてもやりがいを感じますね。

ものづくりに向き合う中で、デザイナーとしての経験も生かされていると感じる場面はありますか?
実感しますね。デザイナーをしていたときは答えがない世界が苦手でしたが、フェンリルに入社しND部でまたデザインに関わるようになり、苦手だった世界を楽しく感じている自分がいました。
その部分には自分の成長を感じましたし、デザイナーとエンジニアの両方の経験が生かされて広い視野でものづくりに取り組めるようになれました。

ものづくりのバトンを繋いでいく
部の設立によって新しい価値が生まれたといえるのでしょうか?
そうですね。ND部が目指す「ものづくり」に適した環境を整えられたことで、全員がさらに高いパフォーマンスを発揮できたと感じています。
それによりフェンリルが大切にしている「デザインと技術で、ユーザーにハピネスを届ける」という考えを、ND部でも体現できているのではないかと思います。
一方で課題に感じていることは?
共同開発部門のようにさまざまなクライアントと関わることはないので、若手メンバーにとってはND部での経験がすべてです。特化したスキルを身に付けることがこの部門の特徴ではありますが、経験値を広げるという点では課題も感じています。
ND部だからこそ得られる専門的な知識やスキルと並行して、メンバーのデザインと技術の幅を広げていくことも考えたいです。
現時点で考えている解決策があればお聞かせください
具体的な解決策はまだ決まっていませんが、理想を言うとND部の良さを取り入れながら、多種多様なクライアントとのものづくりに深く長く関われる体制を新たに作ることです。
そうすることで、あるチームで十分に知識やスキルを身に付けたメンバーは、別のチームに移動し、前のチームでの経験を生かしつつ新しい挑戦ができます。このローテーションを繰り返すことで、結果的にメンバーのデザインと技術の幅を広げられるのではないかと考えています。

また、知識やスキルの習得だけでなく、クライアントごとに異なる会社の文化や雰囲気に触れるきっかけにもなるかなと。その部分も成長の糧になる大切な経験なので、メンバーには知ってもらいたいですね。
課題を解決できれば、フェンリル全体のデザインと技術の幅をもっと広げられると思うので、引き続き最善策を検討します。
ND部のメンバーがクライアントとの関係を築くために意識していることはありますか?
お互いものづくりへの熱量が高いので、ものづくりの障害になりそうなことは、クライアントの意見を伺うだけではなく、こちらからも提案をしながら一緒に解決していくスタイルをとっています。
また、デザインの提案時はディレクターではなくデザイナーが話し、問題の発生時はPMではなくエンジニアが解決策を考えて提案してもらうようにしています。現場のデザイナーやエンジニアが主体的に考えて行動しているので、そういう姿勢もクライアントとの関係を深めるのに役立っているかもしれません。
河岸さん個人が、仕事に向き合う中で心掛けていることはありますか?
PMの立場では、相手の様子をうかがい過ぎたり、変な駆け引きをしたりして時間を無駄にするのは避けたいので、お互い本音で話せる関係になることを意識しています。これはPMを始めた頃から心掛けていることです。

最後に、今後ものづくりの現場で河岸さんが実現したいことをお聞かせください
メンバーが成長できる環境を作る存在になりたいです。自分の若い頃を振り返って思い出すのは、時に優しく時に厳しく接してくれた上司や、責任が重い仕事を任せてくれた環境です。
だからこそ今度は私が、若い世代が成長できるきっかけをたくさん作りたいんです。人の成長は自分のことのようにうれしいし、せっかく一緒に働くことになったメンバーなので、より豊かな人生を歩んでほしいと思っています。これまで周囲の人や環境に助けられてきたので、私がもらったものを他の人やものづくりにおいてお返ししたいです。

河岸 誠二 Seiji Kawagishi
- Editing : Ai Takashima / Haruka Seto
- Photographs : Ikunori Moriwaki
- Location : 丸福樓